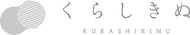お客様が身に着けた瞬間、「心地いい」という感覚に包まれて、自分を慈しむきっかけになるような商品を―。
私たちはそんな想いを胸に、日々商品をお作りしています。
そしてお客様にお届けしている商品は、その一枚一枚に多くの職人さんの知恵と工夫、技術、誠実な想いが込められています。
心地よさの秘密、また商品が生まれるまでの道のりをお客様にもお伝えしたくて、昨年の発売以来、ご好評をいただいている「汗悩みを救う、シルク100%リブインナー」が生まれる背景を辿る旅に出かけました。
シルク100%リブインナーシリーズとは?
まずは、少しだけこちらのインナーシリーズのご紹介を。
シルク100%の素材でありながら、ご自宅の洗濯機で手軽に洗えること。驚くほどよく伸びて、気になる汗のニオイも軽減してくれること。そんな夏にうれしい、頼れるインナーを目指して作りました。
フレンチスリーブ、タンクトップ、ショーツ、レギンスの4つのラインナップをご用意しています。
こちらのインナーは、「糸」から、「編み」「すすぎ(ソーピング)」「縫製」という長い旅を経て、完成します。
今回、私たちの旅を案内してくださるのは、開発担当のダッシーと私が絶大な信頼を置く、アラキニットの荒木さん。あのなめらかな肌触りの生地は、荒木さんの手によって生まれています。
まずは生地の心地よさを探るべく、奈良県のアラキニットさんへ向かいます。
それでは、いよいよものづくりの現場へ!
目次
【編み】やわらかな生地が生まれる場所
機械の設定も、人の手で

こちらが本日案内してくださる、荒木さん。アラキニットさんは1973年、ニットの産地として知られる奈良県葛城市で創業しました。
「シルク100%リブインナー」の他にも、新商品の「絹肌シルクインナー」や「シルク&ウール マルチウォーマー」など、身に着けた瞬間、感動を与えてくれる数々の商品を手掛けてくださる、私たちの心強いパートナーです。
工場に足を踏み入れると、いくつもの機械が規則的な音を立てて生地を編み上げていました。
「シルク100%リブインナーは、丸編み機という機械で編んでいます。」
近づいてみると、そこにはぎっしりと詰まった無数の針が。
「2本並んで両端1本ずつ抜けた針で編むことを業界用語で“ニーイチ”って呼ぶんやけど、この針を抜く作業は全部手作業でやってるから、1本ずつ針を抜く機械の設定だけでも5~6時間かかります。」
糸が、リラックスできる場所
工場内を歩いていると気になるのは、天井に張り巡らされた梁のようなもの。梁の上に糸のコーンが置かれています。

「ここめっちゃ頭ぶつけそうになんねん(笑)歩くのしんどいんやけど、女性のスタッフが糸を繋ぎやすいように、この高さに糸を置いてる。多くの工場は横に糸をまとめて置いてんねんけど、こうして上からゆったり吊るす方が、糸が折り曲がる回数も少なく、ピンと張らない。糸がリラックスできるから、天然素材にはこっちの方がええねん。」
なんて糸想いの、やさしい工夫なのでしょう。荒木さんの工場で扱われるシルク糸は幸せ者ですね…。
和食の職人にも通じる?“銅の釜”
荒木さんのこだわりは尽きることがありません。生地のやわらかな風合いは、実は編み機の「釜の素材」も関係しているのだとか。

「くらしきぬさんの商品は“銅の釜”を使ってる。もう持っている工場はほとんどないけどね。銅は熱伝導率が高いから、温度を素早く上げたり下げたりできる。和食の職人さんと一緒や。なんで銅の鍋使ってるかって言うたら、食材に絶妙な火入れができるから。逆に言えば、腕のある職人さんやから使える道具でもある。生地の場合、鉄の釜だと温度が下がりにくくて、生地が固くなる。生地の風合いを守るために、銅の釜でやってんねん。」
効率だけを求めるのではなく、何よりも大切にするのは生地の「風合い」。そのためには使う道具にもこだわる。その情熱に、ただただ頭が下がります…。
「ここまで気を遣って、熱を発散しやすい銅の釜を作った方がすごいよな。」
ぽろっとこぼした荒木さんの言葉に、ものづくりに真摯に挑む人だけがわかる、職人さんへの深いリスペクトを感じました。
昔からの知恵「牛乳瓶」の秘密
工場を歩いていると、またもや気になるものを発見!機械になぜか、懐かしい牛乳瓶が…。

「これは生地に油分をじっくりじっくり含ませてる。80年も100年も前の人がやってた工夫。最初はマユツバな技術やなーと思ってたんやけど、シャンプーだけよりリンスした方が指の通りがいいように、これをやるとなめらかさが違うねん。油を差すポンプもあるけど、浸透圧で少しずつ染み込ませるくらいが、ちょうどいい。
別にやらなくても編めるけど、でもやったらちょっと違う。その“ちょっと”をやるかどうか。やってみたらよかったから、続けてんねん。
新しい機械が多くなりすぎると、“編むだけ”になってしまう。そうすると海外の生地と変わらない、個性がない生地になる。そしたらおもろないやん?」
働く全人類の心に響くのでは…?と思ってしまうほど、名言がやまない荒木さん。
いくつもの挑戦に裏打ちされた言葉には真実味があり、ひとつひとつの言葉が心に残りました。
最初の工程で、厳しくチェック

生地を編みながら、中から明かりを照らして、ほこりや傷が入っていないかのチェックも行います。
最初の段階で厳しくチェックすることで、後のバトンを受け取る工場に迷惑をかけない。編み工場としてのプライドと思いやりを感じます。
凄まじいスピードで生地が送られていくのに、細かな傷も見逃さない技能に感動してしまいました…!
そうして生まれた生地は、ソーピングの工場へと送られます。
【洗い】ゆっくり、丁寧に
続いて向かうのは、大阪の株式会社V-TECさん。
「シルク100%リブインナー」では、編み上がったばかりの生地をきれいにする大事な工程「ソーピング(洗い)」という工程をお願いしています。
こちらのインナーは糸の段階から染められているため、染色工程はお願いしていないのですが、「シルクはらまき」などの商品はこちらの工場で染色いただいています。創業1933年、老舗の染色工場ならではの知恵と技術が、ここにあります。

出迎えてくださったのは、三浦さん。
工場の中をたくさん案内してくださいました。
 色とりどりのビーカーが並びます。
色とりどりのビーカーが並びます。 染料室は温度と湿度が一定に保たれているそう。
染料室は温度と湿度が一定に保たれているそう。
 毎日朝8時から現場の方と営業担当の方が集まって、今日どこで何を染めるのか予定を立てているそう。
毎日朝8時から現場の方と営業担当の方が集まって、今日どこで何を染めるのか予定を立てているそう。
すべては「正しく量る」ことから
さて、「シルク100%リブインナー」の工程に戻ります。
アラキニットさんで生まれたほやほやの生地は、まず重量を量る場所へと運び込まれてきます。

「生地を台車に載せて、正しい重量を測ります。もし重量が違えば、使う染料や薬剤の量も変わって、出したい色が出なくなってしまう。この重量を量る工程はとても大事なんです。」

黄色く囲まれている白い部分がはかりになっていて、ここに台車を載せて量ります。
シルクを傷つけない、丁寧な「洗い」と「脱水」
いよいよ、ソーピングの工程へ。生地に付着した汚れなどをやさしく洗い流していきます。
もつれないよう、人の手で一枚一枚、丁寧に機械の中へ生地を送ります。


「シルクは本当に繊細。だから、脱水も高速で回さず、ゆっくり、ゆっくり時間をかけます。遠心力で生地が傷んだり、シワになったりするのを防ぐためです。」
美しさを生む「粗繰り(あらぐり)」の一手間
そして脱水を終えた生地は、乾燥させ、「粗繰り(あらぐり)」という工程へ。筒状の生地をきれいに整える、この一手間。

 ※こちらの写真は「シルク100%リブインナー」とは異なる生地です。
※こちらの写真は「シルク100%リブインナー」とは異なる生地です。
「これをするかしないかで、仕上がりが全く違います。うちではこの工程を挟むから、ズレは5mm以内。ほぼ均一に整います。」
この一手間があるからこそ、生地は美しく、より良い状態で次の縫製工場へとバトンを渡せるのです。
【縫製】最後まで人の手で、想いが形に
旅の最後は、縫製工場である奈良県の三岡繊維さん。創業1946年、ここでついに、生地がインナーへと姿を変えます。
案内してくださったのは、専務取締役の谷口さん。なんと、荒木さんの師匠のお一人だというから驚き。
「V-TECさんを紹介してくれたのも谷口さん。編み機の使い方から営業の手法まで、全部この人に教えてもらいました」と荒木さん。
技術とものづくりへの姿勢が、人から人へ、確かに受け継がれているのを感じます。
「寝かせる」ひと手間が生む、豊かな風合い
まずは、生地の裁断から。

「生地が長い状態のまま切ると、裁断した後に生地が縮んじゃう。切る前に生地を小さく切って、しばらく『寝かせて』おくんです。このひと手間が、その後の生地の縮みを抑えて、風合いを保つことに繋がります。」
思わず心の中で「パンみたい…」と想像しながら、ここでも生地想いのひと手間があることを学びました。


一枚ずつ、丁寧に裁断する
小さくカットされた生地を3枚ずつ丁寧に重ね、パターンに沿ってカットしていきます。
「量産なら機械で一気に切るけど、こうして少ない数量でアナログに切る方が、生地にはええねん」と荒木さん。
迷いのない手つきで、するすると生地が切られていく様子は、見ていて気持ちいいほど。
大量生産ならば一度に何十枚も裁断するところを、ここでは3枚ずつ。
その丁寧な仕事ぶりを前にすると、一枚のインナーが出来上がるまでの、見えない時間の積み重ねを改めて感じます。

受け取った生地を、確かな技術で

いよいよ縫製です。ちょうど「シルク100%リブインナー」のレギンスが縫製されていました。
柔らかいシルク生地は、縫うのがとても難しいそう。
「普段は化学繊維を扱うことが多いので、シルクは特に気を遣いますね。しかもこの生地はとにかく柔らくて、いい生地だから(笑)」と谷口さん。

作り手の方にもそう言っていただける生地を、一枚のインナーに仕立てていく。

レギンスのウエストゴムを入れるために、新しいミシンまで導入してくださったのだとか。着心地を良くするためなら、という想いが伝わってくるようでした。
こうして、たくさんの方の手を経て、「シルク100%リブインナーシリーズ」は、ついに完成します。
なぜ、そこまでこだわるのか
旅の最後に、一日案内してくださった荒木さんに、一番聞きたかったことを尋ねました。
「どうして、ここまでやってくださるのですか・・・?」

「くらしきぬのお客様は、違いがわかるから。普通のやり方で満足してくれるお客さんやったら、それでいいんです。でも、くらしきぬさんは商品ができても『もうちょい、こうなりませんか…!』って言ってくるでしょ?(笑)別に小さなこだわりを省いても、生地はできる。でも、その違いをわかってくれる人がいる。そう思うからやってる。
一見、変哲のないインナーに見えるかもしれない。でもお客様が半年、一年と着れば着るほど、風合いが良くなっていく。他のものとの差が出てくる。」
「荒木さんにとって、ニッターというお仕事は天職ですね」と伝えると、
「子供の頃は女性ものの肌着を作るなんて恥ずかしかった。元々、繊維に何の興味もなかった。でもだからこそ固定観念なく何でも質問できて、柔軟に考えられる。今ではチャンスやと思ってます」と笑いながら答えてくださいました。
ここだけの話ですが、荒木さんは昔空手に熱中し、格闘技の世界で生きていきたいと思っていたそう。でも誰よりも熱く、真摯に向き合う荒木さんを見ていると、「天職とは元々あるものではなく、日々の仕事が創り上げていくものなのだ」という気持ちになります。
お客様のことを信頼し、着る人の「心地いい」を叶えるために、全力を尽くす。そして「こっちの方がええねん」の積み重ねで生まれる、くらしきぬの商品。
工場の職人さんと、同じ想いで商品をお届けできていることはとても有難いことで、誇らしく、心強く感じました。
こうして大切に生み出されたインナーが、あなたの毎日に心地よく寄り添えたら、私たちにとってそれ以上の喜びはありません。
「シルク100%リブインナー」で汗悩みを忘れて、すこやかな夏をお過ごしください。
〈取材協力〉
アラキニット株式会社、三岡繊維株式会社、株式会社V-TEC